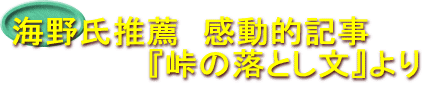
2011.4.21
�C��a�O�Y�搶�A�؍��V���F���Ȋw�����@
�@�@�d�g�]�����V�����K��
�@ ( KASI�F Korea Astronomy and Space Science Institute�j�@
 |
�C��搶��10���N�Ԃ蓌�厞��̊؍����w���ɂ���ɂȂ�ꂽ�B ��������؍��̓V���w�̊J���S���Ă�������q�����ł��B ���N�͊؍��ŏ��߂č��Y���P�b�g��ł��グ��Ƃ̂��Ƃł��B ���������v�Ȃ͋�`�܂ł�������ɋ삯�������̊ԁA���k�� ����܂����B |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
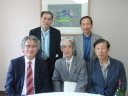 |
 |
| �@�@�P�A���l���@(Kim Du Hwan)S50 �C�m�AS54���m�I���@ �@�@�@�@�@���F��w�F���v�����H�w�ȋ����E�F���J�����ψ��q���̏��ψ���ψ��� �@�@�@�@�@ �@�@�Q�A���j�a(Yu Gye Hwa)S56�C�m�AS59���m�I���@���ԏ��q�勳���i�����w�j �@�@�R�A�␢�t (Jo Se Hyeong)S60���m�I���؍��d�g�V����i������w�L�����p�X��) �@�@�S�A�A�����@(Jeong Hyeon Su)�@H01���m�I���@�d�g�V���� |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
| Korean VLBI Network (KVN) Group The KVN project has been started from 2001. Our KVN will be the first VLBI facility in Korea, which plans to install several cryogenic HEMT receivers working in the frequencies of 2/8, 22, 43GHz bands. Studies have been decided and also the directions to achieve the goals have been studied. The data acquisition system and other interface devices have also been studied. We decided the MIT Haystack Observatory's new Mk 5 as our KVN recorder and made a contract for development of Mk 5. We plan to study this recorder to make copies for our KVN. We also drive forward for international collaborations in several VLBI research areas. The environmental conditions to build KVN observatories have been studied. Especially the radio noise features of the sites are important. So the noise measurement system has been designed and constructed. The site measurements have been made for 2 months. To decide the final locations of the 3 KVN observatories the KVN consulting committee has given recommendations by evaluating the site conditions. This work will be the basic research document for our 5-year KVN project and play an important role in proceeding the KVN construction. Except using for the construction of KVN the other applications could be made after the KVN project has been competed successfully. |
||||
![]()
�؍��V�������@�A�哿�d�g�V����Ɠ��{�̍����V����́A����6���ɁA���ꂼ��̓d�g�]������
�g�p���āA�g��3.7�~�����[�g����VLBI�ϑ��������Ȃ��܂����B�����āA�u�I���I����KL�V�́v
����єӊ��^���ł���u�������ʍ�VY���v����̈�_���P�C�f�ɂ�郁�[�U�[�P���̊��M��
(�t�����W)�����o���A�ϑ��ɐ������܂����B���̔g���ɂ��VLBI�ϑ��̐����́A���ؗ�����
�Ƃ��ĈӋ`�[�����̂Ǝv���܂��B
�@���{�Ŏg�p�����̂́A���쌧��ӎR��45���[�g���d�g�]�����ŁA�؍��̂��̂�1986�N�Ɍ���
���ꂽ��c�s�A�哿�d�g�V�����14���[�g���d�g�]�����ł��B���̗��]�����̋����͖�1000�L��
���[�g������܂��B�V�̂����˂��Ă���d�g�����̂悤�ɋ����̗��ꂽ��ȏ�̓d�g�]������
��M���A���̎�M�M�����������邱�Ƃ��ł���A���̓d�g���o���Ă���V�̂���ɍ���
����\�Ŋϑ����邱�Ƃ��ł��܂��B�������邽�߂ɂ͊ϑ����ʂ���������āA���@�ōĐ�
���đ��֏����������Ȃ�Ȃ���Ȃ�܂���B�ϑ��ɐ����������Ƃ͊����ʂɃt�����W��
�o�邱�ƂŊm�F�ł��܂��B���̂悤�Ȋϑ����@������d�g���@(Very Long Baseline
Interferometry;VLBI)�Ƃ����A�����Ȉʒu�ϑ���V�̂̔��\����˂��~�߂邽�߂ɗp��
���܂��B���̕��@�͖]�����Ԃ̋����������Ȃ�قǕ���\�������Ȃ�A�V�ׂ̂̍����\��
���킩��܂��B
�@����ϑ��ɗp����ꂽ�̂́A��_���P�C�f(SiO)�̏o���g��3.7�~���̃��[�U�[�d�g�ł��B
VLBI�̊ϑ��͔g�����Z���قǍ���ɂȂ�܂��B�g��3.7�~����VLBI�̊ϑ��Ƃ��Ă͂����Ƃ��Z���A
����Ȃ��̂ł������A6��2���̊ϑ��ł́A����Ɍ����ɐ������܂����B���̔g��3.7�~����
�ϑ���ςݏd�˂邱�Ƃɂ���āA�N�V�������̃K�X���o�̃��J�j�Y����A��͒��S�̋���
�u���b�N�z�[���̉𖾂Ȃǂ����҂���Ă��܂��B
�@�����VLBI�ϑ��̐����́A���̌��ʂ����邱�ƂȂ���A�A�W�A�ɂ����āA�g��3.7�~����
VLBI�ϑ���Ԃŏ��߂Ă����Ȃ������ƁA���Ɋ؍��ŏ��߂�VLBI�ϑ��ɐ����������Ƃ�
�Ӌ`�[�����̂�����܂��B���ݍ����V����͓V���L�搸���]�����v��(VLBI Exploration
of Radio Astrometry;VERA)�𐄐i���A��͌n�̐������̒n�}����ڎw���Ă��܂��B���
�؍��ł�VLBI�l�b�g���[�N(Korean VLBI Network;KVN)�����ݒ��ł��B������؋��͂��i�߂A
VERA��KVN���d�ˍ��킹������K�͂̃l�b�g���[�N�ɂ���āA��荂���x�̒n�}�A���
�����x�̓V�̉摜�������邱�Ƃ����҂���܂��B
��4��V�G�l���M�[���E�W����
�@�@�C��a��Y�搶�����z�����d�̎���i��W������܂��B
�@�@6��26��14:00�`14:30 �C��A��ؐ搶�̔��\������܂����B�@�@�@
�@2009�N 6�� 24 ���i���j�`6��26 ���i���j10�F00�`17�F00
�@�� ��F �������b�Z�k���ۓW����/���ۉ�c��l
�@�����J�ÁF PVJapan2009�i���ÁFSEMI�A���z�����d����j
�@�� �ÁF �Đ��\�G�l���M�[���c��
�@�� �ÁF �i�Ɨ��@�l�j�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�A
�@�@�@�@�@�i�Ɨ��s���@�l�j�Y�ƋZ�p�����������A���c�@�l�V�G�l���M�[���c
�@�� ���F �o�ώY�ƏȁA���ȁA���y��ʏȁA�����Ȋw�ȁA�_�ѐ��Y�ȁA�@
�@�@�@�@�@�@�����s�A��t���@
�@�ڍׁ� http://www.renewableenergy.jp/top.html�@
�@
![]()
�u �Ζ��Η͂��i�i�Ɉ����d�͂�
�@�@�� �X�ƊC�Ɛl�̘a�̑��z�G�l���M�[�H�@�� �v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������w ���_�����@�C�� �a�O�Y
���z�G�l���M�[�́A�K�ʂ̐��Ƒ�C�Ɍb�܂ꂽ�n��̐����ɂƂ��Ċ�ւƂ���
���ׂ��V�^�̃G�l���M�[�ł���B
�������A���ΔR���Ɉˑ����������ƂȂ���20���I�ȍ~�̓G�l���M�[���Ƃ��Ă�
���x���s�����ė��Ă���B�Q�P���I�ɂ́A�_�ƂȂǂɂ�鎩�R�̑��z�G�l���M
�[���p����10�{���x�̍Đ��\�ȃG�l���M�[����K�v�Ƃ��邱�ƂɂȂ�B��
�́E���́A�o�C�I�E�}�X�ȂǍĐ��\�Ȏ��R�G�l���M�[���p�͑傢�ɏ��コ��
�邪�A���炭���݂̂Q�{�ȏ�̗��p�̓G�l���M�[���i�̓_�Ŗ�肪������ł�
�낤�B
���̓_�A���z�G�l���M�[�ƒn�M�G�l���M�[�̒��ڗ��p�̌�����10�{�ȏ�ɂ���
�H�w�̊J�����L�]�ł���B
��́A�������͂������Ď��g�ނׂ���K�͌v��Ƃ��āA�n�M�C�m���d����
��B�������n��1000�b�̃}�O�}�̍����ƊC�m��z�̂����炷�R���̖��s����
�[�C�����������Ĕ��d����A�������C��1000�o�[���ł̏��C�^�[�r���̔M�@
�ւƂ��Ă̔��d�����͖w�ǂP�ƂȂ�A�C�m��z�̗��ʂ̖�1000���̂P��p��
�Ēn���S�̂̐l�ނ̎g�p�G�l���M�[���܂��Ȃ��銨��ƂȂ�B
��Q�́A�ƒ�K�͂̏��K�͑��z�G�l���M�[�H�w�ł���B����ł́A���z�����d
�p�l���������~/m2�ƍ����A�Ζ��Η͂ɑR����ɂ�10�{�ȏ�������グ��K
�v������B���d������10 �T��20%���x��80%�ȏ�̃G�l���M�[�͔M�ƂȂ��Ď�
�Ă��Ă���B���z�M������͐^�Ăł�70�����炢�ɂȂ邪�A�~�ł�30�����x
�ŁA���C�̉�����ɂ͂悢�����d�ɂ͌����Ȃ��B
���ҋ��ʂ̌��_��10�{�W���ɂ���Ď�菜���A�Ȃ��c�闼�ҋ��ʂ̌��_�ł���
���퐫�Ǝg�����ő���ėp���Ƃ𑊑ł��Ƃ��A���ꂼ��̒��������Z��
��₦�A���҂̌����ɂ��A�Ζ��Η͂��i�i�Ɉ������d���\�ł���B
�ȈՁu�V�f���X�^�b�g�����P�O�{�W���n�v�z�����d�p�l���̉��i���x
�ő���A�p�l���𐅗₵�ĉ��x�㏸�ɂ������ቺ��h���A���܂���������M
�����u�̗\�����M�Ƃ���A���[�P�T�����̃{�C���[�͒��Ԃ̑��z�M�łP����
�������B
�������A�{�C���[�͑Η��h�~�̊ȈՔS���\�[���[�|���h������p���ĔM������
���Ȃ�����K�v������B�P�O�{�W������Ƒ��z�G�l���M�[���x�͑Γ����x����
350���ƂȂ鐅���̊��ƂȂ�A���z���͐������ł͂Ȃ��A�G�l���M�[����
���Ă̋@�\�����B�Η��h�~�̃\�[���[�|���h�����́A�C�����N�̐i���ʼn��x
�����قǔZ���Ȃ�Η��h�~���ʂŒn���S�̂̕ۉ��ɗp���Ă���A����A�X�͐�
���g���ĕ����������t��CO2�������悭�������Č�������ɂ��Ă���i��
���@�\�j�B�t�Ƃ����\�[���[�p�l���̌������グ��̂ɏW���̑���ɕ���p
�����킯�ł���B
���������ƒ�K�͂ʼn\�Ȑ����ƊC�ƐX�̑��z�G�l���M�[�H�w�́A�W���̌��w
�n�A���d�A�~�d�A�d�C�����ɂ�鐅�f�����A�R���d�r�Ȃǂ̋Z�p�J����K�v��
���邪�A�e���ʂ̊����̋Z�p����̊J���͔�r�I�e�Ղł���B���ΔR���ˑ���
�������瑾�z�G�l���M�[�����ւ̈ڍs�𑁊��Ɏ�������̂��A���{�̐i�ނׂ�
���ł���B
�y �Q �l �z
�ƒ�p�PKW���d�~�d���u�F�i���z�G�l���M�[�F�XK�v�C���d����30%�A�L�����d
���ԁF1/3�j��P���i�J���ʐςX���Q�j�F�R���~�A��P���x���V�f���X�^�b�g
�F�Q���~�A��Q���F�P���~�A��Q���x����F�P���~�A�\�[���[�|�b�g�F�R���~
�A���z�d�r�p�l���i0.3m2�j�F�S���~�A���d�^�[�r���E�~�d�r�F�P�O���~�A�F
�@���v�Q�S���~�i�P�O�N�g���Ό�2000�~�j
������������������������������������������������������������������������
(1) �Ė{�����A�������_ ����10�N1�����B
(2) W.Unno,Publ.Astron.Soc.Japan,14,153-163,1962;ibid.,15,405-411,1963.
(3)�����,���ƌ�����,�_����,1990�B
�S�j����p��Y�E�g�쐳�q,�C����w�T�_,����o��,1979�B
(5)M.G.Gross,Principles of Oceanogrataphy,Prentce
�@�@�@All,7th edd.,1995.
�i�U�jW.Unno and M.Taga,Jpn.J.Appl.Phys.32,1329-1333,1993.
�i�V�j�C��a�O�Y,�����G�l���M�[�Ɗ��̕����w,���{�����w�,
�@�@�@51�727�|733�A1995�BS.Broecker,Science,278,1582-1
=========================================-=====
�C��a�O�Y�i����� �킳�Ԃ낤�j�F������w���_����
�@�@�@�@�@�@�@�@NPO�@�l�������R��w�w��,�V���w�ҁA���w���m
�����F
�@1925�N10��2����ʌ����܂�B1943�N�F������ʌ����Y�a���w�Z�i���E��ʌ���
�@�Y�a�����w�Z�j���� 1943�N�F������ꍂ���w�Z�i���E������w���{�w���j���w
�@1947�N�F�����鍑��w���w���V���w�ȑ��� 1947�N�F������w���w������
�@1952�N8���F������w�t�������V���䏕���� 1953�N4���F���嗝�w��������
�@1963�N4�� -���勳�� 1986�N�ފ� 1986�N �ߋE��w�����B�掖�ِ掖��������
�@���o�āANPO�@�l�������R��w�w���B
�����F�w�V���E�n���E�l���x�i��������1980�N�j
�@�@�@�����w���Ƌ�͂̐��E�x�i��g���X�j�u���̐��E�������˂�v1984�N�j�u����ǓV�E�͕ς�炸�E
�@�@�@��z�K�����x�i���嗝�w���V���w������1993�N�j�w�킽���̊؍��ꎩ�C�@�x�i�������Ёj
�@�@�C��a�O�Y�̖剺���ꗗ
�@�@�@���c���O �������� ����m�� ���،� ���{�� �e�r�� �ߓ����� �c���]�`�� �����N�v
�@�@�@�ĎR���� ����_�� ���{���� ���� ���c���� ���،� �q�c�v �o���C��
�@�@�@�X�o���]�����X�^�b�t�ɊC��剺���������B
������������������������������������������������������
�@�@�n�����g���̓V���w
�@�@�@�@�@������w���_�����E�掖�ِ掖������ �C��a�O�Y
�@�@�@�@�@�v�@�|
| �n�����g���̕����͂܂��n�������ɂȂ��Ă��Ȃ��V���w�̃X�g�[���[�̒i�K�ł���B �n���d�͂̂��ƂŁA���z�G�l���M�[�Ɛ��ő�\�����n�����Ƃ����l�������G�l���M�[ ���A������{���I�ɉ������邽�߂̗��O�ł���B�C�ۊw�ƒn�����w�Ƃ͓������ۂ� �����Ă����_�����ɈႤ�w��ł��邱�Ƃ𗝉�����K�v������B |
�@�@�� �� �� ��
�b�n�o�R�Ƃ����n�����g����荑�ۉ�c(���s)���X�V�N�P�Q���ɊJ���ꂽ�B�Ė{����
�u�����_�Ƃ��Ă̒n�����g���v�i�P�j������ƁA�A�����J�����߂Ƃ��ē�_���Y�f�r�o��
���̌����Ƃ݂Ȃ��A���̌������s�ꌴ���Ŏ��������悤�Ƃ��Ă���Ƃ����B������
�����_�����̔r�o�������̎��тƁA�s�ꉻ���ŗǂ̐����i�ł���Ƃ����ނ�̐M��
����Ƃ������Ƃł���B �푈�ɂ�炸�A���ۉ�c�Ő��E�̍��X�����c�������Ƃ�
�傢�ɕ]������邪�A�n�����g���͗����_�����̂悤�Ȑl�דI����r�I�ɋǒn�����
�e�ՂȖ��ł͂Ȃ��B���g���̌�������_���Y�f�Z�x�����ŕ������łȂ��A���ɓI��
�댯�����悭�킩���Ă��Ȃ��B�N�̖ڂɂ����炩�Ȃ��Ƃ́A�n���������N�������Ē�����
���Ύ������P�O�O�N���������ŘQ��悤�Ƃ��錻��l�̍߈��ł���B ��Ӗ��̂��鐸�k��
����������������n��������邱�Ƃ��A�L���Ȑl���̊�b�ƂȂ�悤�ȁA���l�n�o��
���Ă̎��R�Ȋw�����(�P)���n���������_�@�ɔ��W���邱�Ƃ����҂��悤�
�P. ����CO2�팸��
CO2�͒n�����g���K�X�ł���CO2�팸�͉��g���h�~�̂��߂ł���Ƃ����l������ʂɕ��y����
����BCO2�팸�ɂ͑�^���ł��邪�A�^�����R�͏�������։��ΔR���Ƃ����������c���ӔC��
����i�g�G�l���M�[����P�����h�j�Ƃ����̂��傽�闝�R�ł����āA���g���h�~�_�ɂ��^��
�ł͂��邪�A�^��������Ă���B�ނ���A�����̋^�������܂Ō@�艺���邱�Ƃɂ��A
CO2�����_�@�Ƃ��Ēn�������̍��{�ɔ���̂��ł����X�ɓK���������̐헪��
���낤�B�n�����w�͋C�ۊw���n�߂Ƃ���n�������w�Ƃ͈Ⴄ�w�╪��ł��邱�Ƃ��܂�
�������Ă��������B����ɂ��ẮA�n�k�w�ƒn�k�\�m�w�Ƃ͉��y�Ɖ����w�قǂ��Ⴄ����
�̔F�����n�k�\�m�w�̔��W�ɕK�v���A�Ƃ����ؗF��c����̌����A���̂܂ܒn�����w�ɂ�
���Ă͂܂�B���Ƃ��G���j�[�j���Ƃ��~�J�Ƃ����������l���Ă��Ă��A�C�ۊw�ƒn�����w
�Ƃ͍l���Ă��鎋�_�⎞�Ԏړx�������ł͂Ȃ��B�n�����g���̖{���̖��_�́A�������̕��G
�n�ł���n�����ɑ��ꐡ�������g�����A����ɕs����ȉ��g�����ĂԂ��A���͋t�Ɉ�]
���ĕX���ɓ˓�������S�ɂȂ邩������Ȃ��Ƃ������J�^�X�g���t�B�[�̕|���ł���B
��Q�̒��ӂ��ׂ��_�́A�ő�ŋ��̉��g���K�X��CO2�łȂ������C���Ƃ��������ł���B
CO2�̉������ʂ́A�V�̕����ł͋z�����ѕz���ʂƂ��Ēm�����r�I�ȒP�ȕ����ŁA����
�n�����g���ɑ���P�����ʂ͗e�ՂɌv�Z�ł��邪�i�Q�j�A���͂��̌��ʂ����ɂǂ��͂�
�����邩�ł���B���͉��g���ɑ��đ��i������R������A�܂�������ǒn��������O���[
�o���ȕϓ����[�h������B�����@���ɒn����������Ă��邩�A�܂����̕������c�_���Ȃ�
�Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�Q�D���Ƒ��z
�n���d�͂̏�ɂ����āA���z�Ɛ��Ƃ͋ɂ߂đ������悢�B���̑����̗ǂ�����������݁A
���̐������n���������a�Ȃ��̂ɂ��Ă���B�l�ނ͂�͂葾�z�G�l���M�[���g���A����
�����R�̐ۗ��ɂ���Đ�����ׂ��ł��낤�i�g�G�l���M�[����Q�����h�j�B
�悸�A��C���Ȃ��āA�n�\���M�`���x������̍��̂ł���Ɖ��肵�āA���x�s���A���a�q�r
�̍����t�˂̑��z�ɂ���āA����A���������ďƂ炳��Ă���Ƃ���ƁA�G�l���M�[���x��
�o�����X�ɂ���āA�n�\���xTE��(Rs/2A)(1/2)Ts�A��U���ƂȂ�B���̉��z�W���n�\���x��
�ƂĂ������ɂ悢�l�ŁA�����W���C���ʼnt�̂ł���B�悭�R�O���̔��˔\�����肵�ā|�P�W���A
����ɑ�C�̉������ʂ������ĂP�T���Ƃ����l���������Ƃ����邪�A�L�������ꌅ�̞B������
���������肩��o�������������A���݂̋C�ۂłȂ������̒n��������ɂ���ꍇ�ɂ́A
���m�ɒ�`���ꂽ��L�̉��z�W���n�\���x����Ƃ���ق����悢�B�����ŗp�������S�M�`��
�̂̉���(�ꏊ�ɂ�炸���x���j�́A�������z���̎听���ł�������ɑ��Đ��P�Om����
�ł��퉷�̐ԊO�M�t�˂ɑ��Ċ��S�ɕs�����ł���A��M�e�ʂ��傫�����Ƃŋߎ��I�ɖ���
�����B�����A���[�R�Om�̐��ɂP������������T�O�O�v(���ܓx��������)�̑��z���Œg�߂Ă��A
���x�͂O.�P�����㏸���Ȃ��B���̐��̐��ȏW�~�M��p���n���������A�܂��l�ނ��܂�
���������̃G�l���M�[���Ƃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ͓��M���ׂ��ł���B�P���������ƒ������Ԃ�
�����ɂ́A��Ƃ��đΗ��ɂ��M�G�l���M�[�A���ŗ₦����ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���� ����
�͑Η��̗��̗͊w�������ɉ������ƂɂȂ�A�܂����E�����Ȃǂ��ׂĂ����Ԉˑ��Ȃ̂ň�ʂɂ�
�ʓ|�ł���B�������A�Η��ɍ����������_���g���Q�S���ƉQ�M�`���ϒl�Œu�������āA���E
���������ɌŒ肷��A�P���̐ۓ��v�Z�ňꉞ�������ׂ����x�Ō��ʂ�������B�Ⴆ�Τ
�T�C���I�ȃG�l���M�[���˂ɑ��āA�P���ȔM�`�����f���łW���̂P�̈ʑ��̒x��i�P���ł�
�R���ԁA�P�N�ł�1.�T���j���o����B�������Ȃ���A�����̎戵���ɂ͑�C�Ƃ̑��ݍ�p����
���̉e���A500�T��1000�������Ɛ[�����̑��ݍ�p�A�C����C�m��z�Ȃǔ�Ǐ����ʂ�
�d�v�ɂȂ��Ă���B����������X�̌��ʂ����f�������Ēn���S�̂̃��f���ɌJ�荞�ނɂ͏��
�s�m�������������A�n���S�̂ω����āA�}�C���h�Ȓn����������Ă���̂͊C�m����
���̍�p�ł���Ƃ������_�͕s���ł���B��C����n���ܘ_�d�v�ł��邪�C�ɔ�ׂ�ƕ⏕�I
�ł���B���̗��R�́A��C�͔M�t�˂ɑ��Ĕ������Ŗѕz���ʂ͕s���S�ł���A����P�O��
�̌����̐����炢�̎��ʂ����Ȃ��M�e�ʂ��ɂ߂ď������̂ŁA�C�m���n�Ƃ̔M�������Ȃ���
�Ή��x�ω��̎��Ԏړx�͋ɂ߂ĒZ���B�܂��n�ʂ͋t�ɉ����ɑ��Ă��s�����ł��M�`���x
���傫���Ȃ�����P�N�ϓ��ɑ���X�L���f�v�X����P���A�P���ł͖�T�����A���ω��ł�
�\�ʂ����M��(�₽��)�Ȃ��Ă��n���ɂ͓͂��Ȃ��B���ω��ɑ���ۉ��ɂ͕s���������A
�N�ω��ɑ���ۉ��͗L���ł���B���ꂪ��ː��̉��x���ė₽���~�g�������R�ł���A
���̖��������ł́A����������͊������R�ł���B
�ȏ�q�ׂ��悤�ɁA���̐��ȏW�~�M�@�\���n����������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A����
�@�\�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B���̖O�a���C���͐����̐����ɓK�������x�͈̔͂ʼn��x�Ƌ���
���Ȃ�}���ɏ㏸����B���̂��Ƃ́A���������̏����͈̔͂ŁA�C���ω��ɂ�鐅���C�Ɛ���
�̑��]�ڂ��N���邱�Ƃ��Ӗ�����B���ۤ���̂��鏊�̑�C�͐����C�����Ȃ�̊����Ŋ܂ނ���
��₷�ƉJ�▶����g�߂�Ə����Ă��̊Ԃ̐��M���o���̂ŁA���x�ω��ɒ�R����B�����A
������f�M���x���z���������Ȃ�A�Η���ɂ���̂ł���B����́A���ƒn�\�̉��x��
�����Ȃ��Ȃ�悤�ɓ����B�[�I�Ɍ����A�n�ォ������M��D������Ŏ̂Ă邱�ƂɂȂ�B
�������A����ł́A�n�\�̋C���������Ȃ�ƁA�����C�ʂ������A���ʼn_�����邩��A
���ꂪ���z�����Ղ�A�n�\�̋C���͉�����B����͑��z�Ƃ����M�����O�ɂ��邽�߂̂���
��̌��ʂł���B�������\���ɂ���A�����̒��߂́A�����̐����ɓK�������x�͈͂�
�s����B���͐����̐������������悤�ȉ��g���ɂ����≻�ɂ���R����̂ł���B��������
���_�͖ܘ_�C�ۊw�ɂ��Ȃ��͂Ȃ����A��������邱�Ƃ͖w�ǖ����B�܂��A��ɏq�ׂ����Ƃ́A
�n���d�͂̂��ƂŒ��f�Ǝ_�f���听���Ƃ���P�C���̑�C�ɑ��Ă����邱�ƂŁA�ΐ������
��C�ł͐��藧���Ȃ����A���������Ɗ��i�����l����ۂɂ͒��ӂ��K�v�ł���B
�R�A�A���͗���̐�
����ł́A�C��قǐ��͂Ȃ����A�A��������B�A���̓����Ƃ��ẮA�o�N�e���A���獂��������
���邷�ׂĂ̐����̐H���A�����x����������̏d�v�����܂����������B�������A�A���̓�����
�������ł͂Ȃ��B�A���̗t�̐�߂鑍�\�ʐς͏ꏊ�ɂ���Ă͒n�\�ʐς����̂��A�t�͍�
����z���グ�����𐅏��C�ɂ��đ�C���ɕ��o����B�������̓�������i�Ƒ�������i�R�j�B
���̕��͐��������������Η���p�̈�ł���B���͐���ۂ��A�⋋����B���C�Ƃ������t��
���邪�A�X�т͐��ɊC�Ȃ̂ł���B�X�́A�ė������~�g���ŁA��������ޓ_�ŊC�Ɠ��l�ȓ�����
���Ă���B���̓����̒��S���Ȃ��}�̂����ɑ��Ȃ�Ȃ��B�A���Ƒ��z�ƕ��Ɛ��n�`�̂Ȃ��n��
���낢��ȃX�P�[���ōl�����A�����̗Ή��̖��Ƃ��֘A���A����̊��Ȋw�̈ꕔ��ƂȂ�
�ł��낤�i�R�j�B�M�щJ�т�R���A�����̕��z�ȂǑS�̂Ƃ��ċC�ەϓ��̃��[�h������A�J�I�X
�I�C��ϓ��ݏo���B�J�I�X�I�ϓ��ɂ̓J�^�X�g���t�B�b�N�Ȃ��̂����邪�A�A���̊֗^����
���̂͐��̍�p�Ɠ��l�ɑS�̂Ƃ��Ē��a�̎�ꂽ���a�ȕϓ��ƂȂ鎖�����ҏo���顂��̂��Ƃ́A
�C�ۊw�ł͂�������Ӗ��������Ȃ����A�n�����w�ɂ����Ă͋ɂ߂ďd�v�ł���B
�S�D�n�����͒����G�n�ł���
�n�����S�ʐ��ɕ����Ă�����A��C�Ƃ̑��ݍ�p��C���̉��x�Ɖ��x�Ƃ̓�d�g�U�ɂ��Η���
���Ȃ�̕��G�n�ł���Ƃ͂����A����ł��O���[�o���Ȓ����ϓ��Ɋւ��Ă͔�r�I�ȒP�ȗ��_�I
�戵�����ł���ł��낤�B�������A���ۂɂ͑嗤�̕s�K���Ȕz�u�ɂ��Ǐ���������A����ɋC��
�ň����悤�ȒZ���ϓ��������āA���҂�����^�ŃO���[�o���Ȓ����ϓ��Ƒ��ݍ�p����ƁA�n��
���͂��͂⒴���G�n�ł���A��͓I�Ȏ�@�͕����I�ɓK�p�ł��Ă��S�̂��戵�����Ƃ͕s�\��
����B�Љ�ω��E��C�C�m�ߒ��E�C��ϓ��̉e�����A�����̏d�݂Â��Őv�E�J�������R���s���[
�^�[�ɂ�铝�����f���Ƃ����̂������āA���g�����Ɋւ��Ă̓I�����_��IMAGE�Ɠ��{�̍�����
����AIM�Ƃ��悭�m���Ă���(�P)�Ƃ̂��Ƃł���B���\�ɋy�Ԕ���^���ʂ����_�I���͓��v�I��
��荞�܂�Ă���ƕ������A���炭���f���ɓ����Ă���p�����[�^�͌����_�̃f�[�^���猈��
�����̂ŁA�p�����[�^�̊��S���Ǝ��Ԉˑ����y�уp�����[�^�Ԃ̑��݈ˑ����ɖ�肪����B
�ܘ_�����������f������邱�Ƃ͋ɂ߂ďd�v�ł���A����ɒ����w�͂͂�����]�����Ă��]��
�������邱�Ƃ͂Ȃ����A���f���̓K�����͂����܂ŒZ���I�Ȃ��̂ŁA�P�O�N���ɂ͑啝�Ȍ�����
��K�v�Ƃ�����̂Ǝv���� �����A���N�̑䕗�̔�����P�O�N��̃G���j�[�j���A��N���
�C�m��z�̃��[�h�p�^�[���̕ϓ��Ȃǂ��\���ł��鐸�x�̃��f���ɂȂ��Ă��Ȃ����A�����Ȃ�
���߂ɂ͂���ɍ������̐��k�ȃX�g�[���[������K�v������ł��낤�B�����A�P�N�ϓ��̌n��
�P�O�N�ϓ��̌n�ɤ�P�O�N�ϓ��̌n�͂P�O�O�N�ϓ��̌n�ɤ�P�O�O�N�ϓ��̌n�͂P�O�O�O�N�ϓ�
�̌n�Ƀt���N�^���\�����Ȃ��ĕ�܂���Ă���̂ł���B�܂��A�����ϓ��͒Z���ϓ��̊���
���ē����B�]���āA�n�����G�n�ƌ����Ƃ��ɁA�ǂ̎��_�ɒ��ڂ���̂��悢��������
����B���̎��_�ɉ������K�ȃ��f�����肪�Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���ۏ��ɂ���Ē�`���ꂽ�C��ϓ��Ƃ́A�g�n����C�̍\����ω�������A�l�Ԋ����ɒ���
�ԐڂɋN������A�������Ԃɂ킽���Ċϑ����ꂽ�C��̎��R�I�ω��ɒlj������ω��h�Ƃ���
�邪�A�l�Ԋ����ɋN������ƒ�`�������ł͓�_���Y�f�́A���^����t�����Ƌ��ɁA���g��
�K�X�ł���A���̂����ł��ŋ��̂��̂ł���B�������Ȃ���A�������ʃK�X�i�V�̕����ł���
�z�����ѕz���ʁj�ł����ƁA�ő�ŋ��͎��ɐ����C�ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B�n�����O���猩��ƁA
�n�����猎������悤�ȑ��z���̔��˂Ƃ���ɑ�C�̕��q��G�A�]���ɂ����U�������d
�Ȃ��Ă���B�������A����͓��ˌ��̖�R���ŁA���Ƃ̖�V���̑啔���͉��ԊO�̔M�t�˂ł���B
�M�t�˂͊e�g����Ō��w�I�[�����P�ɂȂ�w(�O������˂����t�˂̋��x���P/���Ɍ��������
����)�̉��x�̍����t�˂ƍl���Ă悢�B�n����C�ł́A���ԊO��̌��w�I�[�����x�z���Ă���
�̂͑啔���̔g����Ő����C�̋z���ł���A�ߐԊO�ɋ߂��ꕔ��CO2�������Ă���ɉ߂��Ȃ��B
CO2�ʂ��Q�{�ɂȂ��Ă��n�\���x�����x���x�̏㏸�ōςނ̂͂��̂��߂ł���B�����A��C��
�̐����C���{������A���ԊO�̌��w�I�[�����{�����A�������ʂ͑����O�a���ē��ł��ɂȂ�
���قڔ{�����邩��A�n�\���x���t�˂������l����S�O�x�قǏ㏸���邱�ƂɂȂ�ł��낤�B
�������A���ۂ͑O�ɏq�ׂ��悤�ɐ����C���Η���ɂ��A�܂��_������A���̓G�A���]��
���q��傫�����đ��z�����˂����炷�B�����C�ʂ̑����͒n�\���x�̏㏸�ɂȂ邩���~�ɂȂ�
���C���A���x�A�C���A�����C�ۂɂ���ĕς��̂ł���B����ɁA�����ǒn�I�łȂ�������
�O���[�o���ɂ���Ƃǂ��Ȃ邩�A�����ƒ����I�ɂP�N�i�n�����]�����j�A�\�N�i���z���_�����j�A
�S�N(���z����������)�A��N�i�C�m��z�����j�A���N�i�X���j���l����Ƃǂ��Ȃ邩�A�\�z��
�ɂ߂č���ł���̂����G�n�̐����ł���B �C��ϓ������Ō��߂邱�Ƃ͕K�v�ł��邪�A
���R�͏��ŋL�q�ł��Ȃ��B�L�q�ł��Ȃ����Ƃ��L�q���Ă���Ƃ����F�������������
�ɂ͕s���ł���B
�T�D��_���Y�f���̏d�v��
CO2���̏d�v���͉��ΔR������ɔ����}���ȋC��ϓ��̖������邪�A�����ƒn���w�I�Ȓ���
�ɂ킽���āA�l�ނ̏����݂̂Ȃ炸�A�n���Ƃ����鐶���̊��ɑ��ďd�v�ł��邱�Ƃ͌���
�܂ł��Ȃ�� ���̏d�v���͒n����C�̐i�����l����Ζ��炩�ł���B���n�̑�C�́A������ΐ�
�Ɠ�����CO2���X�T���ȏ�̈��|�I�ɓ�_���Y�f��C�ł������Ƃ����Ă���B�Ⴂ�������
�̂͑�P�ɐ��̑��݂ł������B������CO2�́A�ŏ��͖��@�I�ɂ��ŃX�g���}�g���C�g�Ȃǂ�
��������t�Y���i�A�T���S�A�L�ނȂǂɂ��\�����N�����ČŒ肳��v���[�g�ɏ���ĐΊD��
�Ƃ��đ嗤�ɖ��߂��܂ꂽ�B��C���Ɏc����CO2�́A���ނ�A���̌������Ő��ƌ������ܐ��Y�f
�Ƃ��Ď�荞�܂�A�]��̎_�f����C���ɕ��o���ꂽ�B���ݑ�C���Ɏc���ꂽCO2�́A�W�O����
�̒��f��Q�O���̎_�f�ɑ��A��0.04���A���ȂǑS���R�₵�Ă���P�������Ȃ����A�C�����ɂ�
���̂T�O�{�ȏオ�n������ł���ƌ����Ă���i�S�j�B�������A���n�̑�C���ɂ͂�����
�Q���������������ƂɂȂ�̂ł���B�X�g���}�g���C�g���������Ŏ_�f���ŏ��ɍ��n�߂��Q�O
�����N�O�̑��z�͌��݂��Q�����炢���x���Ⴉ������������CO2�̖ѕz���ʂ��傫���A�R���N�O
�̐ΒY�I�ȗ���CO2���ۂƑ��z�̑����Ƃ͂قڒނ荇���āA�������͔�������A���ɂ���Ĉێ�
����Ă����B�Ƃ͂����A�Ð��㖖�����I�ƎO��I�̊Ԃ̐�����̑�ʐ�łȂǒn�����̊�@
�����x���n�w�ɋL����Ă���̂������ł���B����قǑ�K�͂ȕϓ��łȂ����A�f���^���ɋN��
����~�����R�r�b�`�T�C�N���̂悤�ȂP���N�I�[�_�[�̕X���ԕX���̕ϓ�������B��C�ƊC�A
�����Ɖ��ΔR���A�����ĊC�m��z��v���[�g�̉^���A�����̊Ԃ̒Y�f�̏z�����낢���
���Ԏړx�ʼn���Ă���B��������CO2�̗��j�����Ă���ƁACO2���̍ŏd�v�ۑ�͊C�m����
�C�m��z�ɂǂ��e�����邩�ł��낤�B����ɂ��Ĉȉ��ɋc�_����B
�U�D�k�ɊC�ƊC�m��z��
�ǂ�قǏ������Ă��}���g������̔M���ʂ�����ȏ�A�����C���Î~���Ă���A�[�����قǐ�����
�������ł���B�������A���̂悤�ȊC�͖k�ɊC�Ɠ�Ɏ��ӂɂ������݂��Ȃ��B�����m�́i�吼�m�
�C���h�m�������ł��邪�j1000�����[���[�C�̉��x�͂R���Ƃ��S���Ƃ��̒ቷ�ł��̂��ߑ�ʂ�
CO2��ێ��ł���B�ቷ�̗��R�͐[�C���k�ɊC�̉����ł���ƍl����Ɨ����ł���B���̖k�ɊC��
�����m�[�C�����ѕt���Ă���̂��C�m��z�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ́A�C�m�����ɂƂ��Ă͏펯��
���邪�A�n�����w�ɂƂ��Ă͒N�ɂ�������C�m��z�̌����̉��߂��K�v�ł���B
�C�m��z�͖k�吼�m�̕\�w���̏����Ɏn�܂�Ƃ���Ă���i�T�j�B�������������C�͑����m���
�J�ƂȂ�A
���x�͑吼�m�ō��������m�ŒႢ�B����ɖk�ɂ���̗₽�����������������āA����ɉ��x���オ��
�ƂƂ��ɗ�₳��A�d���Ȃ��Ē��ݖk�吼�m�[�C���ƂȂ�A���吼�m�C�~��쉺����A�Ƃ�����ł���B
�k�Ɍ��̍~���ʂ͑�z���ʂ̂P�����x�������ł��邩��A���̏��җ��ɂ������͗ʓI�ɐ�����
�L�q�ł���Ǝv���邪�A����ł́A���̑����m�[�C�Ɩk�ɊC��Ƃ��������x�ł���̂��A����
�C�m��z����k��Ώ̂ő吼�m�ԓ����z���Ă���ɓ쉺���C���h�m�����m�ɓ���̂��f�l�������
��������ɂȂ��Ă��Ȃ��B���݂̒n�����̐����ɂ͊ϑ��������������������ł������ł��悢���A
���ω�����ɂ���n�����w�Ƃ��Ă͌������N�ɂł�������X�g�[���[�łȂ��ƕs�\���ł���B
�n�������w�ɂ����铯�l�̌X���̓v���[�g�e�N�g�j�b�N�X�ɂ��݂��A���{�t�߂̃v���[�g�̉^����
�}�O�}�̗₦�ďd���Ȃ����v���[�g�̒��ݍ��݂����ł��܂���邱�Ƃ������
�܂��A�������C�Œn�����]���x���Ȃ�A�������̂����ۂ��������̂��߂Ɏ����W�ɏI�n���Ĉ��ʊW��
���ɂ���Ȃ����Ƃ�����B��������������L�q�ł���ɈႢ�Ȃ��̂����A�ǂ��炩�Ƃ����Ǝ����W
�����X�g�[���[�ɏd����u���n���̓V���w�Ƃ��Ă͕s�����c��B���āA�C�m��z�̓V���w�ł́A
�܂����x�͖k�吼�m����іk�ɊC�ɂ����鍬���ɂ���ď��Ȃ����[�C���Ɋւ��Ă͂قڈ�l�ʼn��x��
��z�ɋy�ڂ��e���͂Q���I�ƍl���顂�������ƁA��z���h���C�u����̂͐��k�ɊC�ō��ꂽ
��C�����ς����č�鈳�͒��߂Ƃ������ƂɂȂ�B�k�ɊC���@���ɂ��ė₽���������̂ł��낤���B
�k�ɊC�̎���͈͂̓V�x���A�Ȃǖk�Ɍ��̑嗤���܂݁A�J�̏��Ȃ��n��ł͂��邪�n���\�ʂ̂P���ʂ���
�\�w���͂��̂��߉��x���Ⴍ�A�Η��͋N���炸���\�ʂ���X���ĉi�v�X���Ȃ��A���̏�ɐႪ�ς����
���z���˂��A�����ł������ܓx�ߓ��˂ɂ��ʐς�����̑��z�����˃t���b�N�X�������Ă��܂��B
�Η���j�~���āA���̗D�ꂽ���z�M�W�~�M���u���\�[���[�|���h�Ƃ������A�k�ɊC�́A���ɗ␅�����
������t�\�[���[�|���h�Ȃ̂ł���B�\�[���[�|���h�@�\�͑��z�G�l���M�[���u�Ƃ��ẮA�����I�ɂ�
���z�d�r�Ȃǂ�y���ɂ��̂������̑��u�ł��邪�i6�j�A�C�m��z�ɂ���Ėk�ɊC���痈�Ă��闘�p
�\�ȃG�l���M�[�͑S�l�ނ̎g���Ă���G�l���M�[�̖�S�O�O�{�ƌ��ς�����i7�j�B
�������A�G�l���M�[���ɂ͂����ł͂���ȏ�G��Ȃ��B�k�ɊC�́A�\�w�łO���ȉ��A�[�C�łR�����x��
����B�k�ɊC��̗≖���́A�k�ɊC����[���吼�m�֗������邪�A�����\���̏������ɒn�т���
�傫���吼�m�n��ɓ���ƒn�����]�ɂ��čs�����A�A�����J���̊C�~�ɐς���B��d�̑傫�Ȑ���
�ς���Ƃ��̉��̈��͂��オ�褐�������̈��͌��z���o����Ƃ��ꂪ���]�̊����́i�R���I���̗ͤ
�]���́j�ƒނ荇�����Ƃ��ł��āA����͍X�ɓ쉺�ł���B���ɂ́A�ԓ����z���č��x�̓A�t���J
���݊��ɓ쉺���A��]�𓌑Q���ē�Ɏ��ӏz�[�C���ƍ������āA�C���h�m�����m�N������B
�����m��k�サ������̓A�����[�V�������œ쐼�Ɍ�����ς��A�����A���Ɨ������Ƃ͈�����i�H��
�吼�m�֖߂褖k�サ�Ėk�ɊC�Ɏ���B���̍l���ł́A�ԓ����z���ė�����k�̔�Ώ͖̂k�Ɍ��S�̂�
�~��~���ʂ���ɑ嗤�ɍ~��ʂ����i�i�ɑ������Ƃ���{�I�ł���B�������A�k�Ɍ��ɍ~��~���ʂ�
�C�m��z�Ɋ֗^���闬�ʂ̋������Ƃ��Ă͂P���ɖ����Ȃ��ł��낤�B�啔���͕��ʂ�z�ł���B
���̂Q�̌����̍����ɂ��Ă͌�ł܂��c�_����B�k�吼�m�̐������ɗ���镔���Ɠ�����k��
����镔���Ƃŗ≖���̌������Ⴄ�Ƃ���ƁA�C��̈��͂���������ƂȂ邪�A���̓����̈��͌��z��
�R���I���͂ƒނ荇�킹�A����n�����قڈꏄ���Ă��ǂ闬���ɉ��������͌��z���z���̑��x�ƗL��
���݂Ƃ̐ς̃I�[�_�[�̉Q�S���ɂ��S���͂ƒނ荇�킹��ƁA���͂̍��͋��ʂ�����A��z�̗���
�͒n�����]���x�Ƃ��Ƃ͗�C���̌��݂�n�����a��吼�m�̕��ȂNJw�I�ʂŕ\�����B�v�Z����ƁA
��z�̎��Ԏړx�͐�N�̃I�[�_�[�ɂȂ�B����͊ϑ��ƈ�v���邩��A���̍l�����͗ǂ������ł���B
����A���̌v�Z����A�k�吼�m�[��4km�ɂ킽�铌���́i���z���R���I���͂ƒނ荇�����߂ɗv�������j
�Ð���������鉷�x�����o���ƁA���̒l��0.1���ɖ����Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��B�ڂ������Ƃ͒m��Ȃ����A
�{���͂��̉��x���͂����Ƒ傫���A��������̉��x�̈Ⴂ�ɑ啔�����E����Ă���̂ŁA�v�Z�㏬����
�l���o���ƍl������B�����ɂ������āA���x�̂��Ƃ������c�_�Ɖ��x�����z�̌����Ƃ�
�k�ɊC�������c�_�Ƃ̗Z����}��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�吼�m�k�[�ƍX�ɂ͖k�ɊC������
�����鉷�x�Ɖ��x�̍����ߒ����c�_����K�v���顂���͑�K�͂ȓ�d�g�U�Η��̖��ŋC�ۂ�
�C��n�`�Ƃ������������G�Ȍn�ŁA���ƂłȂ��Ǝ�ɂ����������Ȃ��B�������A���̖��͌����I
�ɂ͌���\�ł��邵�A�C�m��z�̒n�����Ƃ̊ւ��ɂ͒��ړ����Ă��Ȃ��Ǝv����̂ŁA
����ȏ㗧������Ȃ��B�n�����Ƃ��Ă̖��́A�ŋ�Broecker�i�W�j���w�E���Ă���悤�ɁA
�C�m��z����̈��肵�����[�h�̓����ł��邩�ۂ��ł����āA�Ⴆ��CO2�̉ߏ�r�o���A
����������C�m�z�̃��[�h�̂����̕ʂ̃��[�h�ւ̐�ւ��̈��S�ƂȂ�A���ꂪ�X����
�X���̐�ւ��ɂȂ邩������Ȃ����Ƃł���B
Broecker�̋c�_�͓`���I�ȋC�ۂɂ�鉖�x�̏z�̋c�_����ɂ��������I�C�m�w�̌���łł��邪�A
�����ł͖k�ɊC�N���̊C�m��z���f���ōl���Ă݂����B�����A���g�����N����A�k�ɊC�̉i�v�X
�ŕ����Ă���ʐς����������������Ƃ���B��ɂ�锽�˔\�͌����đ��z�����C����g�߂�B
�}���g������̒n�M�̃t���b�N�X�������ł���Ƃ���ƁA�M�`�����ς��Ȃ��Ƃ������ƂŁA
�Η������̂���\�w�̉��A���ʉ��P�O�O�����x�̕\�ʉ��x���オ�������[�C���x���㏸����B
���̖k�ɊC�����吼�m�ɗ��ꍞ��ō��吼�m�C��̓������͍����ʂ����ăR���I���͂ƒނ�
�����Đԓ����z�����z�ƂȂ�ł��낤���A���ꂪ���ł���B
�C�m��z�̎��Ԏړx����N���x�ł���A�k�ɊC�̑�z���ʂɑ����^����1���Ƃ���ƁA
������ɂ��Ă���N��1���N�̊Ԃ͂قڌ���ƕς��Ȃ��n������ۂł��낤�B�������A
��N�̊Ԃɑ����m�[�C���x�͏㏸���A�����Ă���CO2���C�ɕ��o���n�߂�B�����ACO2�̉���
���ʂ������C�ɋ߂��Ȃ�ƁA���ꂪ�����g���������N�����A���̕s����͎~�܂炸�A���炭
�C�m��z���[�h�͎���ŁA��k�Ώ̓I�z���[�h�Ɉڍs����ł��낤�B���̌��ʂ��X�Ȃ�
���g���Ɍ���������]���Ċ��≻�Ɍ�������������Ȃ����A�ϓ��̎��Ԏړx�͋��炭1���N��
�I�[�_�[�ł��낤�B
���������ϓ��́A�l�ނ���������Ȃ��Ƃ��N���肤��̂��n�����Ƃ������G�n�Ȃ̂�������Ȃ����A
����l����������炸���̂�������������Ă͂����Ȃ��B�����A�l�ނ̎�ŁA�n�����j��̉\��
����邱�Ƃ͏����n���ɐ�����ł��낤�����̂��߂ɋ�����Ȃ����Ƃł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g�G�l���M�[����3�����h�j
(1) �Ė{�����A�������_ ����10�N1�����B
(2) W.Unno,Publ.Astron.Soc.Japan,14,153-163,1962;ibid.,15,405-411,1963.
(3)�����,���ƌ�����,�_����,1990�B
�i�S�j����p��Y�E�g�쐳�q,�C����w�T�_,����o��,1979�B
(5)M.G.Gross,Principles of Oceanogrataphy,Prentce
All,7th edd.,1995.
�i�U�jW.Unno and M.Taga,Jpn.J.Appl.Phys.32,1329-1333,1993.
�i�V�j�C��a�O�Y,�����G�l���M�[�Ɗ��̕����w,���{�����w�,
51�727�|733�A1995�BS.Broecker,Science,278,1582-1
=========================================-=====
�n�����g���u��b�n�Q�_�v�̋���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C��a�O�Y�@
����悵�q���������\�숻�q���������Y�ꂽ���A���E�L���̒n������
�w�Ґԑc���r�ꂳ��̐������p���āA�u�n�����g���͂b�n�Q�ł͂Ȃ��v�Ƃ���
�c�_��W�J������B
���䂳��ɂ���A�\�삳��ɂ���A�����A�����̗��h�ȕ]�_���o���Ă���̂�
�A������c�_������Ɖe�����傫������A���̌����w�E���Ă��������B
�ԑc������̘_���͓ǂ�ł��Ȃ��̂ŏڍׂ͕�����Ȃ����A���䏟�O����́u
�b�n�Q�Œn�����x�͉��x�オ�邩�H�v�i�����Łj�Ƃ����������A�F�l���]����
�Ă��ꂽ�B
����ɂ��ƁA�u�X�͊��i�H�j�i1400�`1800�j����̉ƒn���̏������ϓ�
���啔���ŁA�b�n�Q�����ɂ�鉷�����ʂ̉e���͖�P/�U���x�ł��낤�v�A��
�������Ƃł���B
���ܓx�̕��ϋC����500�N�O�ɂO���A���݂P�T���Ƃ���ƁA100�N�łR��C�A1/6
�@�Ƃ���ƁA10�N��0.5��C���b�n�Q�̐l�ב����̉e���Ƃ������ƂɂȂ�B����
���A�C���ϓ��ɂ͒m���Ă�����̂����ł��A���N�A���N�A�S�N�A�Q�Q�N�A�P
�P�N�A�Q�N�A�P�N�A�P���A���̎����A�������ϓ������邪�A���z���_�����̂Q
�Q�N�i�P�P�N�j�ȉ��̒Z�����ϓ���蒷���������ϓ��̗��_�I�����́A���z��
�ꊈ�������z�G�l���M�[�ߍ���ŕϒ�������ʈȊO�́A�]��悭��������
���Ȃ��B��覐̏ՓˁA�S�n���K�͂̎R�Ύ��Ȃǂ������ƂȂ蓾��ł��낤�B
��Q�̖��_�́A���A�g�Q�n���_���Y�f�A�b�n�Q�Ȃǂ̉������ʂƒn�����g
���Ƃ̍����ł���B���҂͊W�͂��邪�A���ɁA���Ɋւ��ẮA���҂͕ʕ���
�l���������悢�B
��R�̖��́A����`���[�h�i�n�����̔�t�i���j�ł��邪�A������c�_
�ł���m���͎����ɂ͂Ȃ��̂ŁA���\�N�ȏ��̉e���͂����̉���ɂ�����
�c�_�ȊO�́i���炭�N�ɂ��H�j�ł��Ȃ��B
���䏟�O����́A�g����h�̘F�S�M���͐v��S�����ꂽ���ŁA�ڍׂȉ�
�͂ƂƂ��ɁA�ȈՃ��f��������, �O���[�o���ȕ��������𗝉����A�C������
�����Ƃ������@���Ƃ��Ă����Ƃ����B�����ŁA�n�\���x�̊ȈՃ��f���Ƃ��āA
�n�\�ɓ��˂��鑾�z�G�l���M�[�ƑS�n�\�����C�O�֕��˂����G�l���M�[��
���o�����X�����Č��܂鉷�x�ƒn�\���ω��x�Ƃ̍��𐅂g�Q�n�Ɠ�_���Y�f�b
�n�Q�Ƃ̉������ʂɂ�鉷�g���Ɖ��߂��郂�f�����l����B�n�\�ɓ��˂��鑾
�z�����x�́A��C�O�ł̋��x�i���z�萔�j1.37kW/m2�Ɂi�P�|�`�j�i�`�F����
���A�A���x�h�A�ʏ�0.3�Ƃ���j���|�����l���̗p����ƁA���z���𐂒��Ɏ�
���čĕ��˂��鍕���t�ˉ��x��90�����炢�ł��邪�A���z������n�\�ʐ�
�͑S�n�\�ʐς̂S���̂P�Ȃ̂ŁA�����z�G�l���M�[��n�\�S�̖̂ʐςłP
���ȏ�ۉ����čĕ��˂���ƍ����t�ˉ��x�́|18���ƂȂ�B����ƕ��ϋC���P
�T���Ƃ̍��𐅏��C�Ɠ�_���Y�f�̕��q���ɔ�Ⴓ�����������ʂƉ��߂����
�����䎮�ȈՃ��f���ŁA���̊ȈՃ��f�����X�ɍŋ߂̒n�����g���ɓ��Ă͂߂�
�A�l�ׂɂ���_���Y�f�̑��������N��ɂ͉��x�̉��g���ɂȂ邩��\�z����
���Ƃ��A���䂳��̋؏����̂悤�ł���B
�����ŁA���ɖ��Ȃ̂́A�A���x�h�F�`�Ƃ����ʂ̞B���������邱�ƂȂ���A
�h�n�\�������z�G�l���M�[��n�\�Ɉ�l�ȉ��x�̕��˂Ƃ��čĕ��˂���h
���ƂŁA�n�\���M�̒��`���̂Ƃ��Ĉ����Ă��邱�Ƃł���B
�n�\���鑾�z�G�l���M�[�́A���Ɩ�A�G�߁A�ܓx�ɂ�茅�Ⴂ�ŁA�����
���ω�����@�\�͑��݂��Ȃ��B�܂�A�|18���Ƃ����l�͖w�LjӖ��̂Ȃ�����
�ł���B�ǂ����A�ۉ��̗ǂ��n�\���l����Ȃ�A�������A���x�h�F�`=0�ƒu��
�āA�n���������z�萔���S�{�̕\�ʐςŕ��˂��鉷�x�𗝘_�I�n�\���ω�
�x�Ƃ�������悢�B
���̉��x�́A��T���ƂȂ邩��A���E�̒��ܓx�̕��ω��x��P�T���Ƃ̍��P�O
���𐅏��C��b�n�Q�̉������ʂɂ��Ƃ���l�����ł���B
�������A�����Ɨǂ����@������B����́A�n�\���ω��x�Ƃ��āA1000m�Ȑ[��
�[�C���x�R���i276��K�j���̗p���邱�Ƃł���B�R���Ƃ������x�́A�n�M���C
�ʂ֓`������̂ɕK�v�Ȗk�ɊC�ꉷ�x�ŁA�C�m��z���k�ɊC�������Ƃ��āA
�k�吼�m�̓����C��̐����ɂ�鈳�͌��z�ƒn�����]�ɂ��]���͂Ƃ̒ނ荇
���ŁA�k�đ嗤���̐ԓ����z���ē쉺���郂�f���Ő��������B�܂��A�X�ɃA
�t���J����쉺�A��]����ē��Q�A�����m��k��A�A�����[�V���������
���A���{���A��p�E�t�B���s���E�C���h�l�V�A����ʉ߂��Ċ�]��
�ɉ��A�t���J����k��A�\�w���ƂȂ��āA�A�����J���ԓ����z���ē��Q�A��
�[���b�p����k�サ�A���x�𑝂��āA�O���[�������h���ݍ��ޑ�z���f
�����l����ƁA1000m���x�̗����Q�̉Q�S�������肵�āA���a�����̈��͌��z
�Ƃ̒ނ荇��������A�C�m��z�����̊ϑ��l��1500�N�������ł���B
�������A�[�C���x����肵�Ă��闝�R�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B�X�ɁA�d�v�Ȃ���
�́A�C�����ۉ��̗ǂ��ł���B���ˑ��z���̂P�����x�́A���[100m���x�A�g
�Ă��h�ȂǐԂ�����������[���܂œ͂��B���̃G�l���M�[�́A�镪������
�~�G�A�O���ቷ�ɂȂ�ƊC�ʂ���O�֕��o����邩�Ƃ����ƁA��3000�N������
�Ȃ��ƔM�`���ŊO�֏o���Ȃ��B
���̗��R�́A�C�́g���̎w�s���萫�h�Ƃ������i���x�Ɖ��x�́j��d�g�U�Η�
�s���萫�����������N�̐i���̌��ʁA�[�����قlj��x��������d�������̂ŁA
���X�̉��x���z�ł͑Η����N����Ȃ��d�|���ɂȂ��Ă���A���ԊO������
�����̒��q�Փ˂ʼn��x��`����M�`���ł�100m��`������̂�3000�N����
����Ƃ����킯�Ȃ̂ł���B
���̊ԂɁA�C�����Ȃ炵�A��l�����邪�A���̑�\���C�m��z�Ƃ������Ƃ�
�Ȃ�B�n�����g���̉e�����k�ɊC����ς���ƁA���̉e���͖�1000�N�Œn��
�S�̂̐��Ԍn�ɋy�сA�疜�N�����Č��ɖ߂邩�A�V���Ȑi����i�ނ��ƂɂȂ�
���B
���ɁA���Ȃ̂́A���̉e���ł��邪�A���ԊO�ł̐����C�ɂ�鉷�����ʂ���
�邪�A�_�ɂȂ�A�����ɂɂȂ�A�n��ɒB���鑾�z�����U���z��������ʁA��
��X�ƂȂ�A���x�h���ɂ��銦�≻���ʂ������āA���Ɩ�ł��n�㉷�x�ɑ�
�����p���t�ɂȂ�A�����͂��̒n�̉��x�ɂ���Ă����ʂ͕ς��B�n�\�ɂ�
�鐅�̑��ʂ͊C���n�\�̂Q�^�R���߁A����ł͐X�т◤���A���c�Ȃǂ��C��
�������������邩��A�����C�̉������ʂ͓�_���Y�f���傫������Ƃ�����
���A�n�����g���ɑ���e���͑��ߎ��ł͖������ׂ��ł���B
����ł́A�i1400�N�`1800�N�j�̊��������̉Ƃ���������̉��g����
���߂��ǂ��l����ׂ����A�ƌ����ƁA���̊�����͑��z���_�̃}�E���_�[�ɏ�
�����܂ނS�̋ɏ����ɑ������A���{�ł͊��i���狝�ہA�V���A�V�ۂ̋Q�[��
�����ł���A�t�����X�v�������̍��̎��ł������炵�����A1950�N�ɂ͊��S��
���A���Ȃ背�M�����[�ȂP�P�N�����ϓ��ɂȂ��Ă���i���]��h��Y�A�u
���z�v�w�m����2008-�V�j�B���z�G�l���M�[�̈ꕔ���A���z���ꊈ���ɓ]��
���ĂP�P�N������P�O�O�N���x�̕ϓ��Ƃ��āA�\�ʂɌ����ƍl����ƁA���z
���_�̏����ƒn�����Ƃ̑��ւ͐����ł���B
���̂Ƃ���A���z���_�͋ɏ����ɋ߂��A���N�͍��_�̎p�������Ȃ��Ƃ�������
�A�k�ɊC�̕X��O���[�������h�̕X�͂��Z���Ă���̂́ACO2�ɂ�鉷�g����
�A���x�h�̌�����J�[�{���E�n�C�h���[�g�̗N�o�Ƃ������ʂɂ��ƍl��
��ׂ��ł��낤�B���_�ɏ����̊��₩��̉Ƃ������g���̋؏����͍����
���Ȃ�̂��A�g���G�a������ɕ����Ă݂邩�A�g�Ђ̂Łh�̊ϑ����ʂ���
�Ƃɏ�c���v������ɗ\�ĖႤ�����Ȃ����A���̂Ƃ��낻�̋؏�����
���O���āA�����C�Ɠ�_���Y�f�ɂ�鉷�����ʁA�������Ԃ����Ɍ����ēK�p
�������f�����ȈՃ��f���Ƃ���̂��K���ł��낤�B��ԂɌ��闝�R�́A���Ԃ�
�n�\�߂��͑Η����ŁA��C���̉��x���z�́A�قڒf�M���x���z�ł���A���ԊO
���˂ɓ����������ʂ͖w�lje���Ȃ�����ł���B
�@���ɁA�������ʂ̕]���ł��邪�A�t�˕��t�ɂ����C�̉��x���w�́A�n����
�C�̏ꍇ�A���ԊO��̕��ϋz���W���ɂ����w�I�[���̊��Ƃ��ċ��܂�̂�
�A���̕��ϋz���W���ɑ���z�����̊�^�̑傫���������C���_���Y�f�̉�
�����ʂł���B
���ϋz���W���́A�e�g����̋z���W�������̔g����́i�O�����́j�t�˗��ʂ�
�d�݂��������ς��Ƃ�̂ŁA�����z���������������q�����ア�z������
���������q�̕������ϋz���W���ɂ��傫����^����B�܂��A�����z������
�����q���������Ă��w�lj������ʂɉe�����Ȃ����A�����x�ȉ��̋z�����̕�
�q���̑����͂��̂܂܉������ʂɉe������B
�n����C�̏ꍇ�A�����C���q�͂��̉������ʂŊm���ɑ�C�̕��ϋC�����㏸��
���Ă��邪�A���̏㏸�͈�肵�Ă���A�O�L�̓�̗��R�ŁA�����鉷�g��
�ɂ͂Ȃ���Ȃ��B
����ACO2��_���Y�f�́A���ԊO��ɋ��㑽���̕��q�̐U���E��]���[�h�̋z
�����������A���q���̑����͔��I�Ƃ܂ł͍s���Ȃ��Ƃ��A�قڂ��̂܂܁A��
�g���ɂȂ���B���^���n�C�h���[�g�Ȃǂł́A�z�����O�a�ɒB���Ă��Ȃ���
���낤����A���g���ŕ��q����������ƁA���g�����X�Ȃ鉷�g�����ĂԂ�����
������B
�@�����A���̉e���Ƃ��ẮA�_��X��Ƃ��ăA���x�h�ւ̉e��������A���z��
��̏������n�����ɗ^����e���Ƌ��ɏd�v�ł��邪�A���̕ӂ�͐��Ƃ̌�
���Ɉς˂����B
���āA�����P����̈���q�ł������W�F�C���X�E�n���Z�����`�D���C�V�X��
���ɋz�����̑�C�\���ւ̉e�����������Ă������̏��֕��ҏC�s�ɗ��Ă�����
�Ƃ����邪�A�ނ�͍���h�o�b�b�̒��S�I���݂ł���A���⑾�z����̉e����
�ǂ��܂߂āA�b�n�Q�Ȃǂɂ��n�����g���̌����̃��[�_�[�ƂȂ��Ă���B��
���̓��{�l�����̋����҂�����ނ�̘_�����������Ƃ�����B�W�����A�F����
�s�m�̖ї�����ƃe���r�Βk�����Ă����̂��������Ƃ�����B�S�̂������
�A�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂�Ƃ悢�B
���_�Ƃ��āA�Q�P���I�l�ސ����̊�@�����E�����˂Ȃ��n�����g���̍���P�O
�N�Ԃ̓��������߂Ă���̂́A�l�ׂɂ���_���Y�f�̔r�o�ʂł���Ƃ��Ă�
�ڊԈႢ�͂Ȃ��B�����A����ȊO�̗v���������\��������A���ɁA����`
���ʂ����Ȃ��炸����̂ŁA�P�O�N��蒷�������ɂ킽���Ă̗\��͍���ł�
��B���g���̖��̗L���Ɋւ�炸�A�Ζ��Ȃǂ̉��ΔR���͖����̂��߂ɉ���
���ׂ��ŁA����l���Q��邱�Ƃ͌����ċ�����邱�Ƃł͂Ȃ��B�@�@
�i2009/04/07�|16�A5/15�����j
========================================
�C��搶�A�������b�Z�ōu���E�W������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
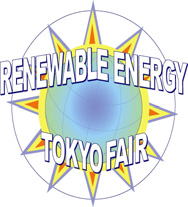 |
��4��V�G�l���M�[���E�W���� �Đ��\�G�l���M�[���E�t�F�A�@ ��ÁF�Đ��\�G�l���M�[���c��
|
�����̎��p�Z�p���L�����J���A�Y�w�A�g�𐄐i���܂��B
6��26���i���j�@��w�E�����@�ւɂ��ŐV�����̐��ʔ��\��
���[�N�V���b�v���ɂčs���܂��B
| �����c�������@�l �������R��w �X�ƊC�Ɛl�̘a�̑��z�G�l���M�[�i���H�w ���\�ҁF�C�� �a�O�Y �� |